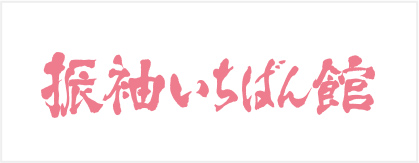事業紹介Business
事業一覧
呉服事業


とみひろ
表参道から山形まで東日本に8店舗展開。本物志向の着物を、紬の産地である山形でつくり、着物の本場 京都から仕入れ、お届けしています。
販売だけではなく、着物で楽しむ時間「着楽会」の企画と開催、大切な着物を綺麗に保つお手入れなど、着物にまつわるお手伝いをいたします。
とみひろ 店舗一覧

庭多泉
〒990-0810
山形県山形市馬見ケ崎2丁目10-23

ろうまん亭
〒990-0039
山形県山形市香澄町2-2-42

東根店
〒999-3711
山形県東根市中央2丁目19-22

寒河江店
〒991-0045
山形県寒河江市小沼町41-1

酒田店
〒998-0853
山形県酒田市みずほ2丁目8番5号

赤湯営業所
〒999-2232
山形県南陽市三間通154-5

表参道店
〒107-0062
東京都港区南青山 6-2-10 バックボーンハウス 1F

大宮店<とみひろふりそで内>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-529-2
振袖事業


TOMIHIRO FURISODE
東日本に7店舗を展開する振袖専門店。振袖のレンタルと購入はもちろん、ママ振袖、写真で成人式プランなどもご用意。当社だけのオリジナル振袖、正統派の古典柄や最新振袖トレンドの振袖など、地域トップクラスの品揃えとサービスをご提供しております。
店舗一覧

とみひろふりそで 山形店
〒990-2453
山形県山形市若宮 1030-1

とみひろふりそで 青山店
〒107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル 西館1F

とみひろふりそで 新宿髙島屋
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿髙島屋 11階呉服サロン

とみひろふりそで 川崎溝の口店
〒213-0011
神奈川県川崎市高津区久本3-1-31 ユーランド溝ノ口ビル2F

とみひろふりそで 本厚木ミロード店
〒243-0013
神奈川県厚木市泉町1-1 本厚木ミロード1 7F

とみひろふりそで 大宮店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-529-2

とみひろふりそで 川越店
〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町 15-18 ニューパレスビル本館1F
フォトスタジオ事業


フォトスタジオ・フェリーク
お宮参り、七五三、入卒などのこども写真から、二十歳のつどい(成人式)の前撮り撮影まで⾏うフォトスタジオ。⼭形・仙台・⻘⼭・大宮の4店舗を展開。店舗毎に趣向をこらしたつくりで、絵本の中のようなアンティーク調、和テイスト、白を基調としたナチュラルな撮影ができる上品な空間などで、多彩な背景や照明を用いて、さまざまな雰囲気の写真を撮影いたします。
フェリーク
店舗一覧

山形店
〒990-2453
山形県山形市若宮1030-1

仙台店
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 Kurax(クラックス)3F

青山店
〒107-0062
東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル 西館 1F

大宮店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-529-2
ウェディング事業


The Little Wedding 一の糸
「小規模な結婚式だからこそ叶えられるアットホームウェディング」をコンセプトに、お蔵をリノベーションした上質で和モダンな雰囲気が特徴の結婚式場です。貸切だからこそ、大切な家族や友人とゆったりした語らいのひと時をお過ごしいただけます。〒990-0054 山形県山形市六日町1−2
営業日時:平日9:30~18:00
定休日:水曜日
カフェ事業


Mulberry Café
2015年、当社が白鷹町で養蚕を始めるべく土地を開墾し、桑を植樹しました。
蚕(かいこ)が桑を栄養にして着物の元である絹ができます。糸が紡がれるように縁が紡がれる場にしたいとの願いから、桑の実の英語名「マルベリー」を店名にしました。
自社桑園でとれた桑の葉を使ったメニューもございます。
-

山形店
TEL 023-681-4885 住所 〒990-0810
山形県山形市馬見ヶ崎2丁目10-23営業時間 11:00〜17:00(LO 16:00) 定休日 不定休 -

東根店
TEL 0237-43-6722 住所 〒999-3711
山形県東根市中央2丁目19−22営業時間 11:00〜17:00(LO 16:00) 定休日 不定休

おきもの屋さんらしく―
陶器や、和柄の手ぬぐい、地紋入りのご祝儀袋やメッセージカードなど、ほんのり和のテイストの小物も。シーズン毎に商品が入れ替わり、和装小物や夏には浴衣が豊富です。
染織事業

染織工芸
自社工房「染織工芸」の紬は、デザイン、染めから織りまでの全工程を、一人の職人が一貫して制作しています。職人は庭や野山で採取した植物を染色に用います。桜、梅、椿などの季節を代表する草木から、紅花、さくらんぼ、リンゴといった山形ならではの果樹まで。四季の変化に富んだ山形の自然から染料を抽出し、一本一本手織りで丁寧に仕上げています。そんな草木染手織り紬は、一つ一つが母なる自然の優しさと力強さを兼ね備えているかのようです。草木の香りがほんのり漂い、紬が持つ優しい風合いと相まって、温もりあるこの世に二つとない逸品に仕上がっています。
和裁事業

和裁工房
とみひろグループ各店で、お客様にご購入いただいたお着物は、「とみひろ和裁工房」で一点一点丁寧にお仕立ていたします。 職人たちは国家資格認定の一級和裁士で、作業は分担せず、一人の職人が反物の裁断から縫製までの全てを担当します。 同じ紬と言えど生地は一つひとつ特色があるため、培ってきた感覚でその生地ならではの特徴を見極めながら、手作業で縫製を行います。
養蚕事業

とみひろ里山養蚕所
とみひろ里山養蚕所は、山形県白鷹町十王地区の里山の土地、約2,500坪の広々とした桑園(そうえん)です。かつて日本のシルクは世界一の生産量を誇り、中でも山形県は近代化以前から養蚕が盛んに行われ、伝統として受け継がれてきました。しかし、日本の養蚕業は衰退の一途を辿り、現在国内に出回る絹の99.8% 以上が輸入品です。日本の近代化を支えてきた何万軒もの養蚕農家は今や県内で5軒を切り、残された農家も高齢化が進んでいます。「安土桃山時代に創業した山形の呉服屋として、日本の伝統的な着物文化を守り、育てていかなければならない」そう考え続けてきた23代目社長冨田浩志が2015年にこの地に巡り合い、土地の抜根、開墾からはじめ、翌年、国内で50年ぶりの新規養蚕農家としてスタートしました。
デザイン事業

デザイン部
社内だけではなく社外の制作も承っております。お問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ロゴマーク/イラストレーション/名刺/パンフレット…等
グループ会社

株式会社ふじや冨宏商事
着物づくりの本場・京都に当社グループの問屋会社「ふじや冨宏商事」の京都支店があり、オリジナル商品の企画・制作や、国内一流メーカーから直に仕入れを行うことで、厳選した質の良い商品を適正な価格でお客様へお届けします。また、この京都支店は祇園祭山鉾の一つである『山伏山』保存会の建物内に在るご縁から、毎年山伏山の組立てから山鉾巡行まで協力させて頂いております。


株式会社 ukitam(NIPPONIA 白鷹 源内邸)
「NIPPONIA」は、日本の原風景を体感して欲しいという思いから、「なつかしくて、あたらしい、日本の暮らしをつくる」という理念を掲げて地方創生事業・古民家再生事業を行っている取り組み。「白鷹 源内邸」(旧奥山源内邸)は江戸時代から200年以上にわたって白鷹町浅立地区に居を構えていた豪農の奥山家一族によって、明治中期から大正初期に建てられた建物群です。縁があり当社が源内邸を受け継ぎ、2021年にリノベーションにより歴史と物語を紡ぐ宿「NIPPONIA 白鷹 源内邸」に生まれ変わりました。敷地内には、離れ蔵、金庫蔵、味噌蔵など母屋を中心にさまざまな造りの蔵が点在しているほか、総面積約 4千坪にも及ぶ広大な敷地内には希少な木々や花々も生育していて、季節感あふれる庭の景色や朝日連峰をのぞむ雄大な風景を堪能できます。